21世紀の老後を支える中核の年金制度に! 現場担当者が見る確定拠出年金制度の改正議論を踏まえた提言
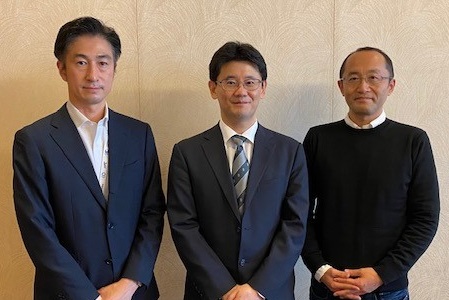
(左)みずほ銀行 伊牟田浩司氏
(中央)フィデリティ投信 浦田春河氏
(右)お金のデザイン 大川原裕二氏
集まっていただいたのは、DC制度(企業型、個人型)の普及の第一線をリードしている大手の運営管理機関みずほ銀行のアセットマネジメント推進部次長の伊牟田浩司氏(写真:左)、「確定拠出年金制度改革提言書」を今年6月にまとめたフィデリティ投信ヘッドオブDCプロポジション&ソートリーダーシップの浦田春河氏(写真:中央)、そして、iDeCoでロボアドバイザーを使った「MYDC(マイディーシー)」を提供しているお金のデザインのDC事業部長の大川原裕二氏(写真:右)。3者3様の立場からDC制度の普及・発展に必要と考えていることを語ってもらった。
◆私的年金は企業型・個人型合わせても加入率が40%程度(生保の個人年金除く)
企業型DCの加入者は723万人(2020年3月末)で民間会社員の16.33%を占めるが、確定給付企業年金(DB)の940万人、厚生年金基金の15万人を合わせても、民間会社員の企業年金加入率は約38%に過ぎない。DCとDBや厚生年金基金は重複して加入できるため実質的な加入率はもっと低くなる。一方、個人で任意に加入できる個人型DC(iDeCo)は加入者が169万人(20年8月)で、加入可能な対象者(第1号から第3号被保険者の合計)6,746万人のわずか2.51%でしかない。
高齢化による年金財政のひっ迫から、公的年金の所得代替率(現役世代の収入に対する公的年金の受給額の比率、2020年度の夫婦の標準で62%)は50%維持を目標に徐々に低下していく方向にあるため、企業年金や個人型DCの加入率の引き上げは大きな社会的課題だ。自助努力の年金準備は、SDGs(持続可能な開発目標)と同様に「誰一人取り残さない(leave no one behind)」取り組みといえる。その点では、多く見積もっても加入率が40%程度でしかない現状は理想からは遠く、「より声を大にしてDC加入を呼びかけなければならない」という焦燥にも似た気持ちがあることは、現場担当者に共通した思いだった。
◆節税以外のインセンティブ
浦田氏は、「自助努力を促すインセンティブが税制優遇のままでは、一部の高額所得者にしか響かない」と語り、「税制優遇という枠から離れた制度設計や普及策を考えるべき」と提言している。たとえば、iDeCoは「3つの税優遇(拠出時・運用時・給付時)」がメリットとして強調されるが、「所得控除は高所得者をより強く優遇する制度であり、所得のない第3号被保険者にはメリットがゼロ。そもそも日本は年末調整で給与所得の税務は会社任せ、会社員は所得課税への感度が低い」として、税控除に代わるインセンティブの創設を訴える。
また、既存の税制ありきで議論するがためにDC制度が窮屈になってしまっているという。浦田氏は「退職所得税制の適用を撤廃してはどうかと思う。退職所得税制は、終身雇用を背景に退職一時金が主要な老後資金でもあった時代に設けられた優遇策だ。転職が当たり前になった今の時代にマッチせず、むしろ雇用流動化を阻害している。企業年金で議論が先送りされている特別法人税の問題を決着させる意味でも、現在の3つの税優遇(EEE型)ではなく、給付時課税を徹底(EET型)する制度設計を考えた方がよい。現状の税制のままでは、一度DCに入ったお金は永久に課税されないことになるので、国としては制度拡充の議論を始められないだろう」と提言する。
退職所得控除については、みずほ銀行の伊牟田氏も問題意識がある。「DC制度がほとんど一時金で一括払いになっているのは、給付時の課税にも課題があると考えられる。退職所得が控除に加えて2分の1しか課税されないなど有利な条件である一方、年金で受け取ろうとすると、公的年金やDBの給付で公的年金等控除の枠を使い切ってしまってDCでは控除枠をそもそも使えない人がいる。退職所得控除を廃止しないまでも縮小して、例えば年金として受け取っている間は繰り延べ可能で最後に課税されるなど、もっと年金受け取りを促進する税制への見直しができると良い」と感じている。
さらに、浦田氏は「掛金の全額所得控除も見直した方が良い」という。「掛金を全額控除できてしまうルールのままでは、拠出額の拡大=税優遇の拡大となる。しかし、現在のひっ迫した財政状況を考えれば、枠の拡大が簡単に実現するはずがない。一方で、国民の間で自助努力の機運は確実に高まっていて、制度がこれを満たせていない状況だ。そこで、税控除は一定水準に限定しつつ、それを超えても個人のニーズに応じて自由に積み立てできるようにすべき。つまり、税引き後拠出を解禁するということだ。これは、生命保険料控除などと同じ仕組みであり、何も新しい考えではない。外国でも全額控除対象ではないことが一般的だ」と語る。システム上の管理の負荷については、「税引き前拠出金」と「税引き後拠出金」の2つのサブ口座を持つことは、現状で「企業型DC」と「個人型DC」という2つの口座を1人が持つのと似た構造であり、複雑なものとはならないのではないかという。毎年の所得控除は、政策的に普及が求められているマイナンバーを使って処理するようにすればいいのではないか、とも提言する。
◆より簡便な加入手続きのために
一方、全ての手続きをオンラインで進めたいと考えているお金のデザインの大川原氏は、「マイナンバーをDCの加入手続きに使って、現在議論されている必要書類を一度紙にプリントアウトして、記入捺印後にスキャンして電子媒体で送るといったような煩雑な手続きでなく、画面上で必要項目を入力するだけで加入手続きが完結する環境を用意してほしい」と訴えている。この手続きの簡素化については、新しく発足するデジタル庁の力も借りて社会インフラとしてのDC年金の管理システムを業界の共通プラットフォームとして作れないかと提言している。マイナンバーについては、非常に厳格な情報管理が求められるため、現場の対応は難しいかもしれないが、利便性が大幅に高まり、金融機関と行政機関のコストも削減されるものであれば、業界が動くかもしれないとしている。
また、現実問題としてiDeCoは、加入者にとって手続きに手間がかかり、金融機関にとっても短期的には収益が低く(加入から数年は実質赤字になることも)、一部の金融機関では取り扱いに消極的なところもある。みずほ銀行は運営管理機関手数料の無料化や運用商品の拡充など積極的な取り扱いを続けている背景について伊牟田氏は、「銀行の多くのお客さまは、まだまだ資産運用には慎重で、ゼロ金利時代でも定期預金のみで運用されている方もいる。ところが、老後の準備をしていますかと問いかけ、税メリットなどをご説明すると、多くのお客さまがiDeCo加入を検討していただける。そして、iDeCoを始めたお客さまは10%~20%の方が他の運用商品も購入されるようになる。貯蓄から資産形成にお金を動かすことは金融機関の大きな課題だが、iDeCoは突破口として期待できる」という。
◆DC開始20周年を前にフレームワークから議論を
日本でDC制度が始まって約20年。この間、拠出限度額の引き上げ、加入対象者の拡大、事務手続きの簡素化など、様々な工夫や改善を重ねてきた。過去の制度や他の社会保障制度との整合性を保つことを意識しながらの制度設計になったため、iDeCoなどは勤め先によって拠出限度額が異なるという複雑な姿になっている。海外のDC制度にも詳しい浦田氏によると、「日本より遅れてDC制度を導入したアジア諸国の方が、よっぽど整理されて使いやすい、かつ、限度額も十分に確保した素晴らしいDC制度を運用している。日本は、つみたてNISAが始まったことで似たような小粒の積立制度が並立し、分かりにくさが増してしまった。DC20周年を機に、本当に日本人の老後不安を取り除くことに資する制度にするため、大きなフレームワークから考えて現在の制度を根本から作り直すタイミングに来ているのではないか」と語っていた。
そして、浦田氏は、税優遇に代わるインセンティブのアイデアとして「政府マッチング拠出」をあげている。たとえば、iDeCoに毎月1万円を拠出すると、そこに政府が5,000円を上乗せ拠出するというような運用だ。英国やドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシアなどで採用されている。マレーシアでは20代、30代だけに限定し、オーストラリアでは低所得者だけに限定するなど、対象を政策的に絞ることも可能だ。また、国によるマッチングが難しければ、事業主マッチングを解禁すべきだとも提言している。
伊牟田氏は、「社会保障審議会での議論は、様々な制約がある中、DC利用者拡大のために制度を前進させており、評価すべきだと考えている。ただ、すでにDCやiDeCoを利用している人が利用できなくなるような改定は制度を安心して利用してもらうためにも避けるべきだと考える。これからの自助努力の社会保障について、金融機関として何ができるのかについては、関係する各社で真剣に考え、業界横断的に議論して良い方向を探っていかなければならない」と語っている。今回、議論に参加していただいた3人は、それぞれの立場でDC制度とは20年近いかかわりを持ってきている人たちだ。その議論を聞いていると、DC20周年を迎える2021年を前に、DC制度は「日本人の老後を支える制度」に相応しい姿へと脱皮することが切に求められていると感じられた。
【関連記事】
・みずほのiDeCoが運用商品を大幅拡充、アクティブファンドが充実し運用の楽しみ増える
・資産形成を「自分ごと」にするため加入者エンゲージメントの向上を=フィデリティDCセミナー
・iDeCoにローン、「MYDC」がSOMPOホールディングスと提携して加入者向けローンを提供開始
バックナンバー
- 株安と円高で純資産総額は6カ月ぶりに減少、「S&P500」連動型への資金流入目立つ=DC専用ファンド(2025年2月) ( 2025/3/12 12:00)
- 「S&P500」など先進国株式インデックスファンドに資金集中、iDeCo新規加入者は2倍増=DC専用ファンド(2025年1月) ( 2025/2/12 10:50)
- 「S&P500」連動型インデックスファンドに資金流入が加速=DC専用ファンド(2024年12月) ( 2025/1/15 09:05)
- 1,500億円を超える大規模な資金流入を記録=DC専用ファンド(2024年11月) ( 2024/12/11 15:16)
- 米国株式の上昇で外国株式インデックスファンドの人気が盛り上がる=DC専用ファンド(2024年10月) ( 2024/11/13 14:33)
- 46カ月連続の資金流入が継続するも流入額上位ファンドの顔ぶれに変化=DC専用ファンド(2024年9月) ( 2024/10/09 16:03)



